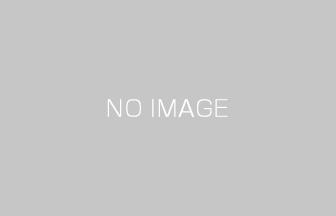※当ブログにはプロモーションを含みますが、記事内容は公平さを心がけています。
20世紀を代表するマルチ作家マルセル・パニョル(Marcel Pagnol)の自伝的小説『少年時代の思い出(原題:Souvenirs d’enfance)』を原作にした映画があります。
1990年に劇場公開されフランスで大ヒットした、『マルセルの夏(原題:Le gloire de mon père )』です。
現在でも、毎年夏のバカンス中にテレビ放映される定番の家族映画で、フランス人が大好きなバカンスをテーマにした作品になります。
みなさん、こんにちは!3月くらいから「夏のバカンスの予定」を考えてワクワクし始めるフランス人が可愛いと思ってしまうカタクリです。
この記事では、『マルセルの夏』のあらすじと、映画から垣間見れる20世紀初頭のフランス社会問題についてご紹介します。
※当ブログにはプロモーションを含みますが、記事内容は公平さを心がけています。
夏休みの思い出が人生の宝物になった映画『マルセルの夏』のあらすじ
マルセイユ出身の小学校の教員ジョセフ・パニョル(Joseph Pagnol)と、お針子のオギュスティーヌ・パニョル(Augustine Pagnol)との間に生まれたマルセルは、学校に隣接した公務員用宿舎に住んでいたため、幼い頃からオギュスティーヌが外出する際、ジョセフが授業を行う教室に預けられていました。
3歳になったある日、マルセルは突然、黒板に書かれていた文字を読み、父親ばかりではなく周囲の子供をも驚かせました。
しかし、勉強をしすぎると熱が出ると信じていたオギュスティーヌは、マルセルが小学校に入学する6歳まで、本を読むことを禁じてしまいます。
その頃、身体が弱かったオギュスティーヌを手伝うため、家事や子どもの世話をしていた彼女の妹のローズ(Rose)が、マルセルを連れて行った公園で出会った年上の男性ジュール (Jules)と恋に落ち、 二人は結婚することになりました。
敬虔なカトリックであったローズとジュールは、毎週日曜日に教会のミサに参加した後、必ずパニョル家に訪れるのが習慣になります。
しかし、リベラルで無神論者であったジョセフは次第に苦痛を感じ始めていました。
とはいえ基本的にみんな仲良く、マルセルが9歳になった夏、パニョル一家とローズ・ジュール一家はガルラバン山塊にある別荘を借り、初めて「バカンス」を過ごすことになりました。
大自然の生活に興奮する子どもたちをよそに、狩りが得意であったジュールは狩初心者のジョセフに指導をはじめます。
ジュールから容赦無く厳しい指導を受けている父親の様子を見たマルセルは、それまで全能だと思っていた父が急に情けなく見えてきました。
そして父親の名誉のためにも、マルセルはジョセフの狩りをサポートすることに決めたのでした。
映画『マルセルの夏』に見る、20世紀初頭のフランス社会
古い価値観から新しい価値観への変化が激しかった20世紀初頭。
映画『マルセルの夏』には、そんな激動時代のフランスが見事に描かれています。
ここでは映画のシーンを通して、20世紀初頭のフランス社会、特に学校のシステムについて見ていきましょう。
小学校教育の無料・義務教育・非宗教性
1882年に、公共小学校の教育において全ての国民に対して無料・義務教育、そして非宗教性を強化という内容の、ジュール・フェリー法(Loi de Jules)が制定されました。
それまでは教師といえば、カトリックの神父やシスターでしたが、この法律が制定されると、教育免許を取得した一部のエリートのみに許された職種となりました。
教師は人々の信頼を集める職業で、特に田舎では崇められた職業でした。
映画の中で小学校教師であったジョセフが、授業中にテクノロジーや文明の進歩などを讃え、義理の妹夫婦のように信仰が熱い人たちや、村で出会った神父のような宗教家を受け入れられない姿勢を見せていたのは、このような背景があったからです。
フランスで長く続いていた男女別学制度
2021年現在でも、古くに建てられた校舎の入り口をよく見ると、男子用(Garçons)と女子用(Filles)と書いてあることに気が付く人も多いのではないでしょうか。
それらは、1975年に「男女共に机を並べて同じ教育を受ける」ことに重点を置いたアビー法(Loi Haby)が制定される以前の名残です。
1850年には女子初等教育が義務付けられていましたが、長い間「男子は軍隊訓練、女子は縫い物を習う」事を中心に、男女別々の校舎で学んでいました。
バカンスを楽しめるのは一部の人たちだけだった
1904年の南仏が舞台になっている『マルセルの夏』では、ジョセフとジュールは、ともに公務員だったおかげで「2ヶ月のバカンス」に出かけることができました。
しかし当時のフランスでは、一般企業で働く労働者には週休制度も適応されていなかった時代なので、そう考えると彼らがいかに特別な存在だったかということに気がつきます。
今でこそ「フランス人はバカンスの為に生きている国民」と言われますが、一般企業で働く人が自由バカンスをもらえるようになったのは、1936年になってからだそうです。
とはいえ、バカンスをもらえるようになっても、当時はまだ「移動自体の出費」が高かったため、バカンスに出かけることができるのは一部のお金持ちだけでした。
第二次世界大戦後にようやく労働に関する法律が改正され、1956年には年間3週間から始まった有給休暇が、1982年に現在のように最低5週間になりました。
有給休暇の日数が増えた80年代からは、手頃な値段で長期滞在ができるキャンピング場などが増えてきたため、一般庶民もバカンスを楽しめるようになったそうです。
父と息子の愛情が伝わってくるシーン
映画の原題『Le gloire de mon père(僕のお父さんの栄光)』
が示す通り、この物語のベースとなっているのが「父親と息子のつながり」です。
二人の絆を最初に感じるシーンが、マルセルが文字を読むシーンです。
いつものようにジョセフの授業をおとなしく聞いていた3歳のマルセルは、教壇に立つ父の姿を誇らしく思っていました。
そして、父が黒板に書かいた文字を、マルセルは思わず声に出して読みます。
驚いたジョセフは、本当に息子は字を読んでいるかテストするために「Le papa est fier son petit garçon qui sait lire.(父親は、字を読むことができる小さな息子を、誇りに思っている)」というフレーズを黒板に再度書きます。
それを見たマルセルが
Ça, ça veut dire que tu m'aimes bien ?
それ、それってお父さんが僕のことを大好きっていうことでしょう?出典:『マルセルの夏』
このマルセルの回答で、彼が3歳にして字が読めるだけでなく、その文章の意味も理解していること、そして彼が自分への愛を確信していることを知ったジョセフは、普段は論理的で合理的でクールな表情ですが、目の前で奇跡が起こったように、息子を見る詰める表情が印象に残るシーンになっています。
まとめ
家族映画を代表する『マルセルの夏』は、今でも毎年夏休みにテレビ放映されるほどの人気を誇ります。
劇作家・映画脚本家・映画プロデューサにして、アカデミー・フランセーズのメンバーという華麗な経歴を持つ、小説家マルセル・パニョルの幼少時代の話がモチーフになっており、フランス人なら誰しもが共感する「子どもの頃のバカンス体験」が見事に描かれています。
ただ、村の住民たちの南仏訛りのフランス語はかなり強烈なので、聞き取りが難しいかもしれません。
特に、マルセルの友達になるリリー(Lili)の南仏訛りは、私が今まで聞いてきた中でもトップレベルの難解さです。
そのため、フランス語の学習教材としてみる場合は、フランス語字幕をつけて鑑賞することをお勧めします。
一見大きな事件は起こらず、淡々と話が進んでいくように見えますが、登場人物たちのセリフや態度を通して、社会的に大きな変革の渦中にあった20世紀初頭のフランスをさりげなく描いているあたり、さすがはパニョルと唸らせられてしまいます。
この映画は約100分と短いので、1回目は映画の雰囲気を楽しむために、2回目はフランス語を聞き取るために、3回目は登場人物の態度をよく観察して当時の社会背景を読み解くために、など何度も繰り返して観ることをお勧めします。
見るたびに新しい発見と学びがある、そんな素敵な映画です。

フランス・パリ在住の、気分は二十歳の双子座。
趣味はヨーロッパ圏内を愛犬と散歩することと、カフェテラスでのイケメンウォッチング。
パリ市内の美術館ではルーブル美術館、オルセー美術館とポンピドーセンターがお気に入り!
好きな映画は70代80年代のフレンチ・コメディ。
オススメや好きな作品は詳しいプロフィールで紹介しています。